対象読者:小〜中規模の個人・家族農家(ねぎ作付 5–40a/総作付 5–80a、労働 週8–20時間、家族1–3名体制、年売上 300–1,200万円目安)/副業で単価を取りにいきたい人
この記事でわかること
- 端境期(はざかいき)の正体と、価格が跳ねるメカニズム
- “狙う週”から逆算する作型の設計手順(10ステップ)
- 作型の強度を上げる3レイヤー(品種×環境×流通)
- 東海〜関東の平坦地(中間地〜暖地)向けモデルカレンダー
- ねぎ・にんにく・しょうがの端境攻略メモ(副業×週2日稼働対応)
- よくある失敗パターンと回避策、チェックリスト
小〜中規模の目安(数値)
- ねぎ作付面積:5–40a(片区5–20a×2面のイメージ/例:B18a・C15a)
- 総労働時間:週8–20時間(週1–2日)
- 人員体制:1–3名(家族中心)
- 年間売上:300–1,200万円(ねぎ比率高め/加工含む)
- 機械規模:中型管理機(5–8PS)+半自動定植機(トラクターは外注でも可)
端境期とは?
市場での供給が薄くなり単価が上がりやすい“すき間週”。
- 典型例:**初夏(4月下旬〜5月)と初秋(9月〜10月)**は多くの品目で谷ができやすい。
- 価格が上がるのは“希少化”と“品質のバラツキ増大”の二重効果。安定品質で出せるだけで勝てる期間です。
端境を獲る考え方はシンプル:
- 狙う週を決める(曖昧に月ではなく“第◯週”まで落とす)
- そこから逆算し、播種・定植・被覆・追肥・収穫のトリガーを設計
作型設計の10ステップ(逆算式)
- 価格が高い“週”を仮決め(過去2〜3年の相場メモでOK/体感でも可)
- 狙い週の幅を設定(最低2週、できれば4週連続で波状出荷)
- 品種特性を整理(耐暑・耐寒・抽苔、日長反応、栽培期間)
- 育苗/定植時期の候補を2つ以上(早着手・本命の二刀流)
- 環境ギミックの選択:マルチ(黒/銀/透明)、不織布・トンネル、遮光、ベタがけ、敷き藁、かん水頻度、畝高・暗渠
- 施肥設計:生育曲線に合わせ、狙い週にピーク品質が来るよう追肥を前後させる
- 分割定植・分割収穫:同一作型を2〜3バッチに小分け
- 収穫前の“調整余地”を用意:被覆の開閉、灌水、刈り上げタイミングで±7〜10日の調整幅
- 出荷形態の複線化:JA・直販・契約・加工(乾燥/発酵/貯蔵)
- 週2日運用の動線設計:固定曜日で回る週次ルーティン表を作る
端境に強い“3レイヤー”
- 品種:抽苔しにくい・耐暑/耐寒の明確な系統を選ぶ。ねぎは夏越し強い長白系、しょうがは早生/晩生で収穫波を作る、にんにくは早生〜中晩生を組み合わせる。
- 環境:
- 温度:トンネル・ベタがけ・遮光(30〜40%)・マルチ色で微調整
- 水分:暗渠+高畝で過湿回避、点滴でリズムを作る
- 光:銀マルチ・敷き藁で地温/反射光コントロール
- 流通:貯蔵(キュアリング)、加工(黒にんにく)、規格バリエーション(長さ・束数・カット)で**“売れる週”を増やす**
モデルカレンダー(東海〜関東の平坦地)
目安。年ごとの気象で±2〜3週のズレを想定。
| 月 | ねぎ | にんにく | しょうが |
|---|---|---|---|
| 1–2 | 冬どり最盛。貯蔵・規格分けで単価確保 | 休眠・低温貯蔵 | 貯蔵しょうが販売(薬味/加工) |
| 3 | 春先の端境入り口:軟白・若どり需要 | 活着準備(種球選別) | 種しょうが伏せ込み準備 |
| 4–5 | 初夏端境:抽苔管理・遮光で品質維持 | 新物の葉にんにく〜生にんにく | トンネルで初期生育加速 |
| 6–7 | 夏越しの山。遮光+灌水で倒伏回避 | 収穫・乾燥・キュアリング→黒にんにく加工 | 追肥・敷き藁で地温安定 |
| 8–9 | 秋口端境:B区(夏どり後半)/C区(冬どり定植開始)—分割定植が効く | 乾燥球出荷/加工切替 | 新しょうが開始(高値期) |
| 10–11 | C区(冬どり)立ち上げ/B区は更新・畝準備 | 黒にんにく安定出荷 | 新〜中しょうが最盛 |
| 12 | 冬どり安定。選別で単価維持 | 加工品・ギフト需要 | 貯蔵切替・温湿管理 |
圃場イメージ(A/B/C)
- B区:夏どり1作(目安:7–9月)。高畝+暗渠+遮光30–40%で倒伏・抽苔を抑える。
- C区:冬どり1作(目安:11–2月)。風よけ・ベタがけ→トンネルで保温、遅れ年は被覆で+7〜10日調整。
- A区:他作・輪作(例:菜の花/にんにく・しょうが等)。端境補完や土づくりに活用。
品目別:端境攻略メモ
ねぎ(長ねぎ)
- 狙い週:B区(夏どり)7–9月/C区(冬どり)11–2月。端境は7月前後と9–10月に山が出やすい。
- 設計
- 1作×2面(B=夏どり/C=冬どり)+分割定植:各区を2〜3バッチに分け、波状出荷を作る。
- 環境:高畝(25–30cm)+暗渠。不織布ベタ→トンネル→遮光へ段階切替。夏は30–40%遮光。
- 作業省力:定植機×中耕管理機、雑草は抑草マルチ+通路除草ロボで週2日運用。
- 品質調整:倒伏前に軽い土寄せ、収穫前7–10日でかん水/被覆で節間を締める。
- 保険:
- 規格複線(太・中・細/長さ別)で“外れ週”も売り切る。
- 夏の高温年は**出荷遅らせ(遮光+軽いかん水)**で端境週へ寄せる。
にんにく
- 狙い週:生にんにく(5–6月)と乾燥球の端境(9–10月)。加工で通年化。
- 設計
- 品種分散:早生+中晩生。抽苔タイプ/無抽苔を混ぜ、収穫を波状化。
- キュアリング:収穫後21–28日で乾燥→貯蔵。ここで端境を“作る”。
- 加工:黒にんにくで在庫を価値化。低コスト化の鍵は断熱・均熱(庫内温度±1–2℃)。
- 保険:過湿は病気の元。暗渠+高畝+敷き藁で玉太り維持。
しょうが
- 狙い週:**新しょうが(8–10月)と貯蔵しょうが(冬〜春)**のつなぎ目。
- 設計
- 早生/晩生をミックスして波を作る。
- トンネル+敷き藁で初期地温を確保、梅雨期は排水最優先。
- 規格:根茎サイズ別、葉しょうが規格も用意して端境前後を刈り取る。
- 保険:貯蔵は温湿管理(12–14℃/高湿)でロス低減。
週2日稼働でも回る“週次ルーティン”(例:土・日のみ)
- 土曜(畑日):除草(ロボ稼働確認)→中耕・土寄せ→被覆開閉→定植/追肥→収穫Aロット→出荷準備
- 日曜(仕上げ日):収穫Bロット→選別・規格分け→箱詰め→月曜AM出荷(JA/契約/直販)→加工(黒にんにく庫の巡回)
分割定植×分割収穫で“端境4週連続”を狙う。各バッチは7–10日ずらし。
よくある失敗と対策
- “月”で設計してしまう → 第◯週まで落とす。週の粒度が端境攻略の最小単位。
- 単一作型・一発勝負 → 2〜3バッチに分解し、被覆で速度調整。
- 水管理軽視 → 端境期は極端気象が多い。暗渠・高畝・点滴で再現性を確保。
- 出荷先が単線 → 規格・チャネル複線(JA+直販+加工)。“売れる週”を増やす。
- 省力化の後回し → 週2日運用では機械の段取りが生命線(定植機・中耕管理機・除草ロボ)。
チェックリスト(公開前の最終確認)
- 狙い週が4連続で設定されている
- 同一品目で2品種以上を採用
- **分割定植(7–10日差)**の設計がある
- 被覆・遮光・灌水で±10日の調整余地を確保
- 出荷チャネルが2つ以上、加工・貯蔵の選択肢あり
- 週2日で回るルーティン表ができている
ひな形テンプレ(コピペ可)
狙い週:第__週〜第__週(__月)
品目/品種:__/__
作業計画:
- 播種:__月__週
- 育苗:__℃・__日間/硬化:__日
- 定植:__月__週(バッチ1)/__月__週(バッチ2)
- 被覆:ベタ→トンネル→遮光(__%)
- 追肥:__月__週/__月__週
- 収穫:__月__週〜__週(A/Bロット)
品質トリガー:節間・太り・葉色/被覆開閉の基準
出荷先:JA ___ / 直販 ___ / 契約 ___ / 加工 ___
まとめ
端境期は“運”ではなく設計で作る季節。品種×環境×流通の3レイヤーを組み合わせ、
第◯週まで落とし込んだ逆算設計と分割バッチで、週2日でも“高単価4連週”は十分に獲れます。まずは1品目でよいので、来季の端境4週をひな形で設計してみてください。
この記事の前提:ねぎはB・C区(田んぼ2面)で運用します(A区は他作に使用)。以下の表記はB/Cに統一しています。
追記(運用メモ)
- 圃場条件:元田の転作は暗渠+高畝が最優先投資。ねぎ・にんにく・しょうが共通で効く。
- 設備:定植機/中耕管理機/除草ロボ/(黒にんにく庫は断熱・循環優先)。
- 販売:ギフト・規格差活用・加工で“売れる週”の幅を広げる。
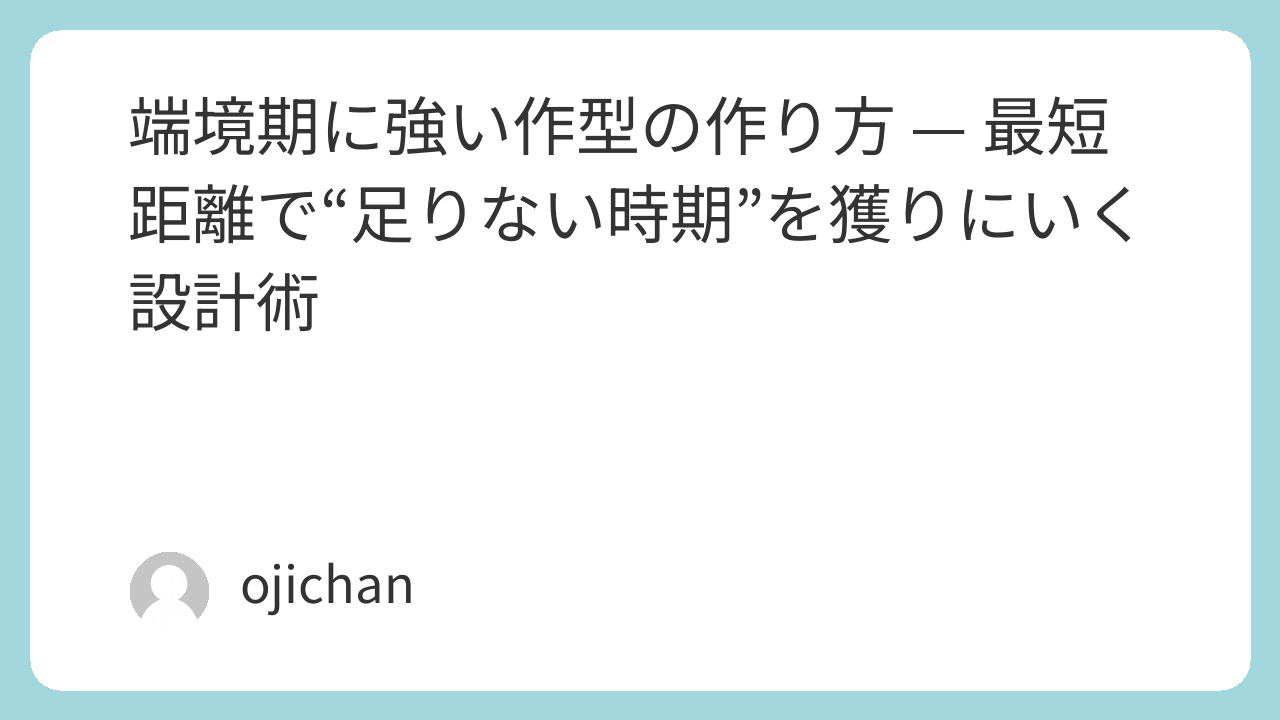
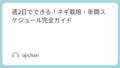
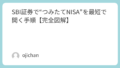
コメント