「いくら積み立てるのが正解?」に終止符。
可処分所得 → 生活維持 → 守り → NISA の順に流す“3レイヤー配分”で、家計に無理のないNISA額を一発で決めます。
TL;DR(先に結論)
推奨NISA月額
N = MAX{ 0, T×(1−σ) − L − M }
- T:手取り月収(可処分)
- σ:安全マージン(初期は10〜20%)
- L:ベース生活費=固定費 E + 変動費の最低ライン Vmin
- M:守りのキャッシュ = 年払い引当 S(/12)+ 緊急資金の毎月積立 r + 高利負債の追加返済 D
- r = MAX{0, (L×目標月数 − 現在の緊急資金) ÷ 積立期間(月) }
まず「生きるコスト」と「守り」を確保。余力がそのままNISAです。
3レイヤー配分とは?
- 生活維持 L:住居・通信・保険などの固定費+最低限の変動費
- 守り M:年払いの引当/緊急資金の積立/高利負債の返済
- 攻め(NISA):上の2つを満たして残った余力を投資に
配分の順番がすべて。投資額は“残り”で決めると、破綻しません。
ステップバイステップ(5分で設定完了)
STEP1|手取りTと安全マージンσを決める
- T=世帯の手取り月収
- σ=10〜20%(昇降給・物価・想定外の出費を吸収)
STEP2|ベース生活費Lを出す
- L=固定費E(住居・通信・保険・教育の最低ライン)+ 変動費Vmin(食費・日用品の最小値)
- “最低ライン”で見積もるのがコツ(見栄は入れない)
STEP3|守りMを計算
- 年払い引当 S(月換算)=年額/12
- 緊急資金:目標(月数)を決める(最低3〜6ヶ月)
- r=MAX{0, (L×目標月数 − 現在残高) ÷ 積立期間}
- 高利負債の追加返済 D(リボ・カードローンなど)
STEP4|NISAの“推奨月額”を算出
- N=MAX{0, T×(1−σ) − L − M }
STEP5|年間目標とのすり合わせ
- 「今年の投資目標(年額)」を置き、(目標−ボーナス充当)÷12 と N を比較
- 小さい方を“毎月の実行額”にする(無理なし運用)
ここまでを自動化したテンプレ(Excel)はこちら 👉 NISA逆算テンプレをダウンロード
速算ルール(超忙しい人向け)
- 緊急資金が3ヶ月未満:NISA=余力の50%まで
- 3〜6ヶ月:NISA=余力の70%まで
- 6ヶ月以上:NISA=余力の100%(ボーナスで年払い補填も◎)
- 高利負債(実質年率7%超):まずは返済を優先
具体例(リアル家計でシミュレーション)
例A|単身:手取り25万円
- 前提:E=11万、Vmin=6万、年払い=12万(=月1万)、緊急資金=15万、目標=3ヶ月、積立期間=12ヶ月、D=0、σ=10%
- L=17万、S=1万、r={(17万×3−15万)÷12}≈2.0万、M=1万+2.0万=3.0万
- 余力:T×(1−σ)=22.5万 → N=22.5−17−3.0=2.5万円
例B|共働き子3人:手取り60万円
- 前提:E=25万、Vmin=11万、年払い=48万(=月4万)、緊急資金=60万、目標=6ヶ月、積立期間=24ヶ月、D=0、σ=10%
- L=36万、S=4万、r={(36万×6−60万)÷24}=3万、M=4万+3万=7万
- 余力:T×(1−σ)=54万 → N=54−36−7=11万円
- 年間目標が120万円、ボーナス充当20万円なら:
- 必要月額=(120万−20万)/12=8.33万円
- 実行額は「MIN(11万, 8.33万)=8.33万円」(無理なく目標達成)
ストレステスト(やっておくと安心)
- 収入−10%:Nは機械的に減額(式にT×(1−σ)が効く)
- 物価+5%:Vminの再見積り→Lが変わればNも自動調整
- 年払いの増加:Sを上げれば、その分Nが下がるだけ。破綻しない
“逆算式”の良さは、家計変動に合わせて投資額が自動で適正化されること。
よくある落とし穴3つ
- 生活費を“実績値”で入れる(ムダ込み):最小限で見積もる
- 年払いを忘れる:車検・保険・学費・旅行・家電更新は年間引当に
- 安全マージンをゼロにする:初期は**10〜20%**を死守
いますぐ出来るチェックリスト
- 固定費の見直し(通信・保険・サブスク)
- 変動費の“最低ライン”を家族と合意
- 緊急資金の目標(月数)と積立期間を決める
- 年払いの棚卸し(合計→12で割る)
- 式に入れて“毎月のNISA額”を確定
- ボーナスでの年払い・投資補助を設計
CTA|テンプレ使って3分で決めよう
- ✅ Excel版:入力すると自動で推奨NISA月額と実行額が出ます
- ✅ 家計簿アプリで固定費・最低ラインを“見える化”→月1回だけ見直し
まとめ
NISAの積立額は“気合”ではなく“式”で決める。
まず生活維持と守り、そして残りが投資。
ルール化すればブレないし、家計が変わっても迷いません。
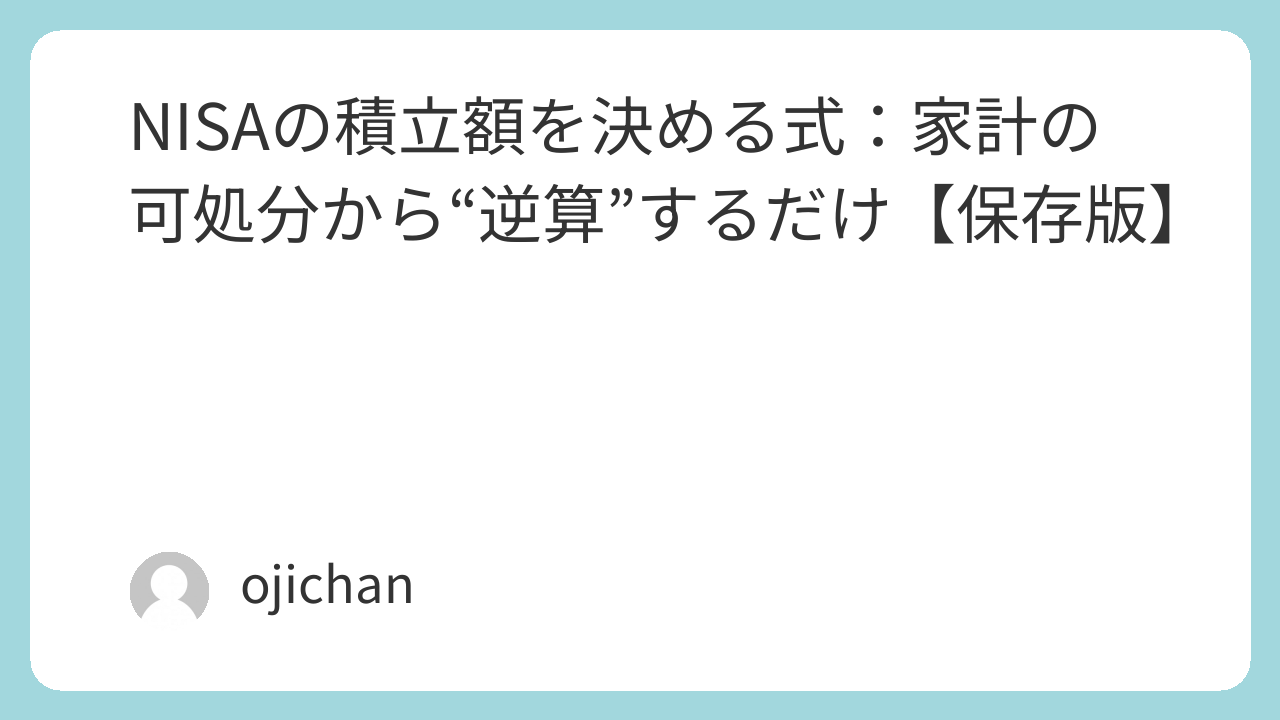
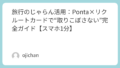

コメント